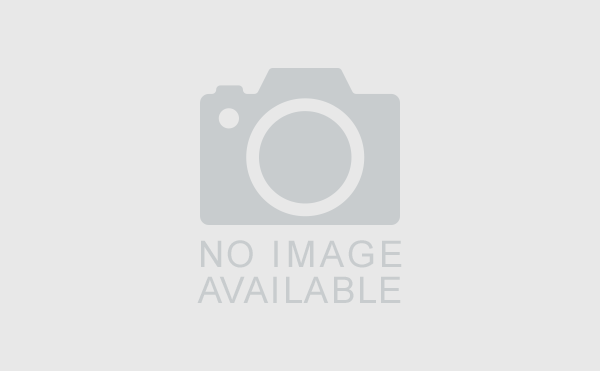薬価という制度について考える
日本には「薬価」という制度があります。
これは新しい薬が研究・開発されて発売される際に、国がその値段を定める仕組みです。たとえば、新薬の薬価が1,000円と設定されると、その薬はしばらくその価格で販売されます。
しかし薬価は、昔は2年に1回、現在では1年に1回見直され、平均で毎年5〜8%ほど値下げされていきます。
1,000円で発売された薬が、翌年には930円、さらに年々下がり、10年も経てば100円ほどになることもあります。
これは一般的な経済の原理とは逆で、商品の価格が下がり続ける珍しい現象です。
確かに薬には特許期間があり、最初は高い価格が設定されるものの、その期間が過ぎると価格は大きく下がります。
ですが、実際には「100円で売れ」と国が指示したとして、製薬会社がその価格で薬を供給し続けるのは非常に厳しい状況です。採算割れや赤字が生じるケースも多く、
――このままでは薬の安定供給が難しくなり、患者さんの手元に薬が届かなくなる恐れが出てくるのです。
そして今、現場では実際にこうした薬の供給問題が多数起きています。
一部の薬が不足したり、製造中止となるケースが増え、現場ではとても深刻な影響が出ています。
これは患者さんにとっても無関係な問題ではありません。
薬価の仕組みや背景、そして現実に困っている現場の声にもぜひ目を向けていただきたいと思います。
今後どのようにこの問題へ対応していくか、国や製薬会社だけでなく、患者自身も知識を持ち理解を深めることが大切です。
このコラムが、薬価制度の現状と課題について考えるきっかけになれば嬉しいです。